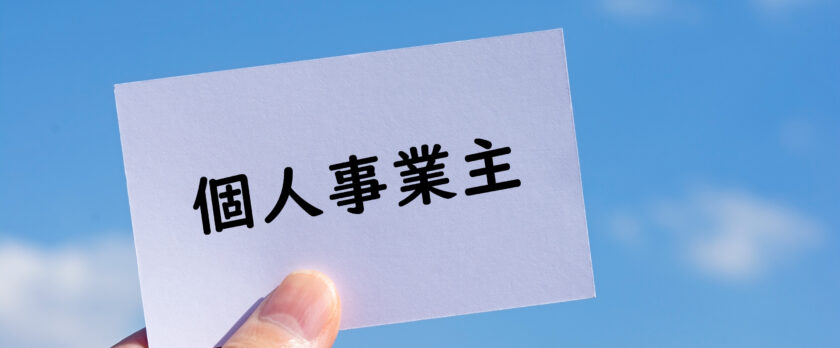こんにちは。東京都よろず支援拠点 コーディネーターの上條紘輝です。
よろず支援拠点で相談業務をしていると、「漠然と、税務・会計周りが不安だから…」、という理由でお越しになる方がいます。もちろん、そのようなご相談も大歓迎です。
お受けすることの多い相談ですので、開業を検討されている方に向けて少しでもご参考になればと思い、今回まとめております。
なお本ブログは、「個人事業主」として開業される方向けのお話です。法人を設立して事業を開始する方、もしくはどこかでお勤めの方が副業として事業を開始する場合などは、話が変わりますのでご注意ください。
今回は、以下2点についてお伝えします。
A.開業に際し提出すべき書類について
B.事業開始後に継続的に行う作業について
A.開業に際し提出すべき書類について
東京商工会議所様が発行する資料では大変丁寧な解説をされているため、本資料を参考にされると良いと思います。
【参考】「開業ガイドブック」(東京商工会議所)
>「STEP8会社をつくる」>「②開業に必要な届出(法人と個人)」
https://tokyo-cci.meclib.jp/kaigyou_book/book/#target/page_no=45
提出すべき書類が網羅されていることもあり、様々な書類について言及がありますが、多くの方が提出を検討される、次の2つの書類について触れていきます。
a.開業届出書
b.青色申告承認申請書
提出書類の準備については、税務署に備え付けの書類が置かれていますが、以下のURLより印刷して記入し、提出をしていただくのでも問題ありません。
【参考】「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
【参考】「所得税の青色申告承認申請手続」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
a.開業届出書
書式に則って記入していきます。こちらを提出しておくことで、確定申告時期などには税務署より案内が届くようになります。
b.青色申告承認申請書
多くの方が開業届と一緒に提出をされます。ただ、青色申告を行う際の作業負荷など考慮し、ご自身が青色申告の適用を受けるべきか、少し立ち止まり検討することをお勧めします。
青色申告には様々な特典があります。例えば「青色申告特別控除」は、最大65万円を所得金額から控除することが可能で、本制度が最も知られているという印象です。
ただ、この「青色申告特別控除」の恩恵を最大限受ける場合、「複式簿記」での記帳が必要となります。
この「複式簿記」は、経理作業に馴染みのない方にとって非常にハードルが高いと個人的には感じます。開業する前に、簿記について勉強をしたことがある方なら別ですが、そのような方は少数派ではないでしょうか。
こうした実情を踏まえ、経理作業に馴染みのない方に提案している選択肢は次の二つです。
1. 青色申告会や東京商工会議所の指導をうけながら複式簿記による記帳を行い、青色申告を行う。
2. 青色申告は実施しない。白色申告を前提とした記帳を行い、白色申告を行う。
【参考】青色申告会
https://www.tokyo-aoiro.or.jp/
【参考】東京商工会議所 記帳指導
https://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/kicyo/
1. は、青色申告会などの支援機関の指導を仰ぎながら複式簿記を行い、青色申告を行う方法です。
開業初年度は所得がマイナスになる可能性も比較的高いことを考慮すると、「純損失の繰越控除」(翌年度以降への純損失の繰越し)も青色申告の特典として検討すべき制度となるでしょう。「青色申告特別控除」や「純損失の繰越」など青色申告制度のメリットを最大限享受したい方は、1で述べた方法がお勧めです。
2. は、青色申告の特典よりも、白色の記帳作業の容易さを重視する方法です。
参考URLを掲載しますが、白色申告の場合に要求される記帳のレベルは高くありません。
白色申告の場合、年間の収入と必要経費の整理が完了し、税務署の確定申告会場も活用すれば、ご自身で確定申告を行うことも可能と考えられます。
税務メリットよりも、まずは自分の力で確定申告まで完結させたい、と考えられる方にとっては有効な選択肢かもしれません。白色申告を行う際は申告時に、「収支内訳書」という書類に収入や必要経費をまとめることとなりますが、URLを掲載しますので参考に御覧ください。
【参考】帳簿の記帳のしかた− 事業所得者用−(国税庁)
>「Ⅰ白色申告者の帳簿とその記帳のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
【参考】令和6年分 収支内訳書(一般用)の書き方(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/034.pdf
【参考】令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r06/kakushin_kaijo/index.htm
次に、以下についてお伝えします。
B.事業開始後に継続的に行う作業について
作業全体を総括すると、「記帳を行い、税務申告を行う」と言えるでしょうが、記帳や税務申告については今までの話で所々触れてきました。
相談をお受けした際は補足として、入出金の記録(請求書、領収書などの証憑類)の保管方法についてお話しするようにしています。
領収書等の保管方法は人それぞれです。厳格な定めがあるわけではありません。
ただ当方からは、例えば税務署の方から、
「帳簿記載の、●年●月●日、相手先▲▲▲、金額■■円のこの領収書を見せてください。」
と依頼をされた際に、迅速に用意・提示ができる整理を行う方が良い、というアドバイスはさせていただいております。
これについては、少なくとも年度ごとに書類を分け、日付順に整理しておけば、対応できるのではないでしょうか。
また、業務用の預金口座を設けることもお伝えしています。
記録を付けるという観点からも、業務の入出金の中にプライベートの入出金が混ざると整理が大変になります。業務用の通帳として一つ用意し、業務用の通帳にある情報を全て記録・集計する方が事務負担やミスを減らすことにもつながります。
以上、ご相談時には上記内容などをお伝えしていますが、いかがでしたでしょうか。
まずは大枠を捉えて、細かいところは徐々に学んでいくという考え方でも良いかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
皆様のよろず支援拠点のご利用、お待ちしております。